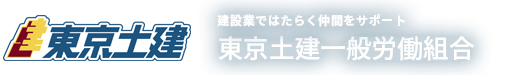中央執行委員長談話
戦後80年を迎えて
どう伝えていくか 戦争の記憶と平和教育
東京土建は、アジア太平洋戦争の傷跡も生々しい1947年に結成されました。組合の立ち上げに関わった諸先輩方は、戦争に建設職人が駆り出され、職人の技術・技能が人殺しのために使われた経験から「二度と戦争のための工事をしない」という言葉を残しています。
なぜ、組合が平和運動を進めるのか、それはこのような歴史があるからです。
日本は今年2025年、戦後80年を迎えます。この大変重要な節目の中で行なわれた参議院議員選挙の結果は、国民の審判により自公与党の過半数割れという結果となりました。この間の物価高騰対策に手立てを講じない、または裏金問題の解決も何もないことへの国民の怒りとも言えます。しかし、より右傾化した政党の出現もあり、改憲勢力も3分の2を超えており、平和憲法が大きな危機を迎えております。
戦争体験者が少なくなるなか、戦争の記憶や平和の尊さを次世代にどう伝えていくかが大きな課題です。平和教育の充実、戦争遺跡の保存、証言の記録などがより一層重要になります。また、 日本は憲法9条を持つ平和国家として、国際社会においてどのような役割を果たしていくべきかが問われます。
世界各所での国際情勢不安は ロシアのウクライナ侵攻やガザ・イスラエル紛争など、日本の安全保障政策や平和運動のあり方が改めて重要になっています。
アジア諸国との歴史認識の問題も、あらためて向き合うべきテーマですし、しっかりと過去を直視しつつ、未来に向けて平和な関係を築くための努力が求められます。
日本の平和運動は今、特に重要となっています。特に憲法第9条の堅持。この憲法第9条が持つ意義や未来について、さらに大きく語るべきです。
あらためて唯一の戦争被爆国として、日本は非核三原則を掲げ、核兵器廃絶を強く訴えなければなりません。また、沖縄をはじめとする米軍基地の存在は、本当に日本の安全保障と平和に寄与しているのか。基地負担の軽減や、地位協定の見直し、そして日米安全保障体制のあり方そのものが問われているのではないでしょうか。
戦後80年、日本の平和運動がこれまでの活動を振り返り、来るべき未来に向けてさらなる前進と発展を想い、今後の世代を担う若者たちたが活発な議論と行動が展開されることを改めて期待します。

東京土建一般労働組合
中央執行委員長 中村 隆幸